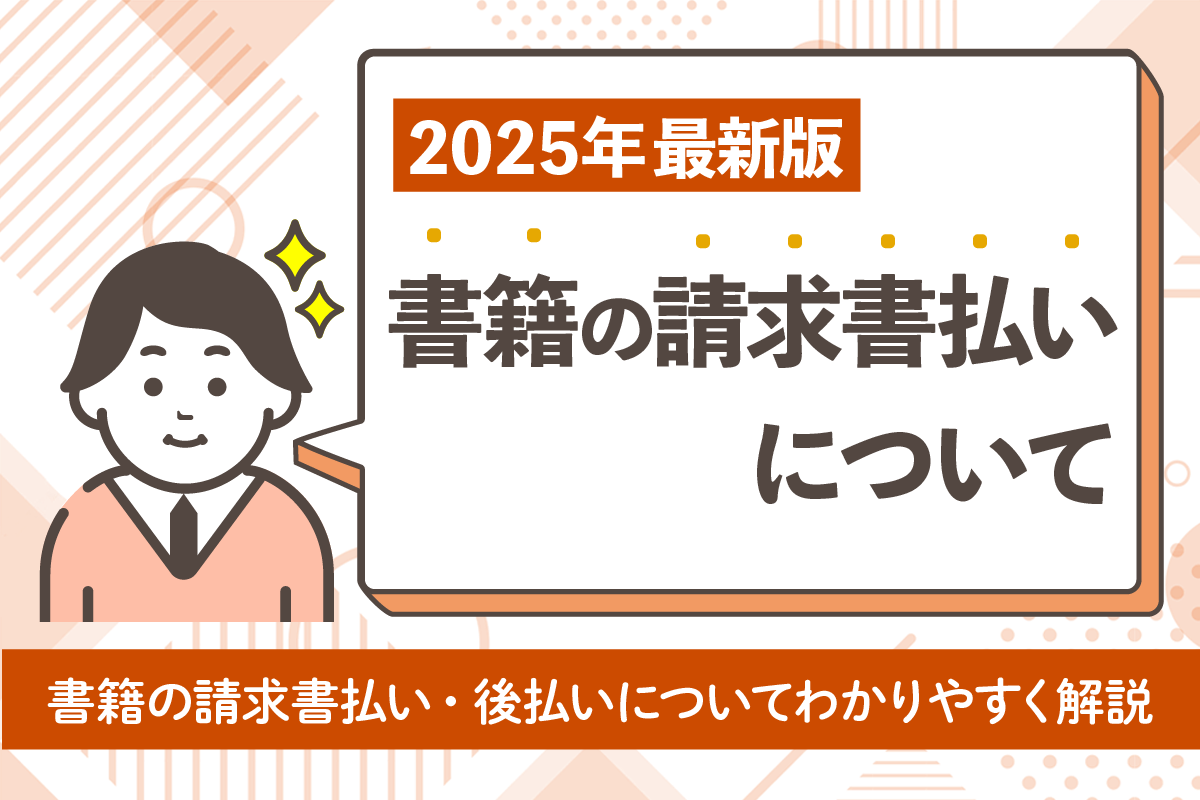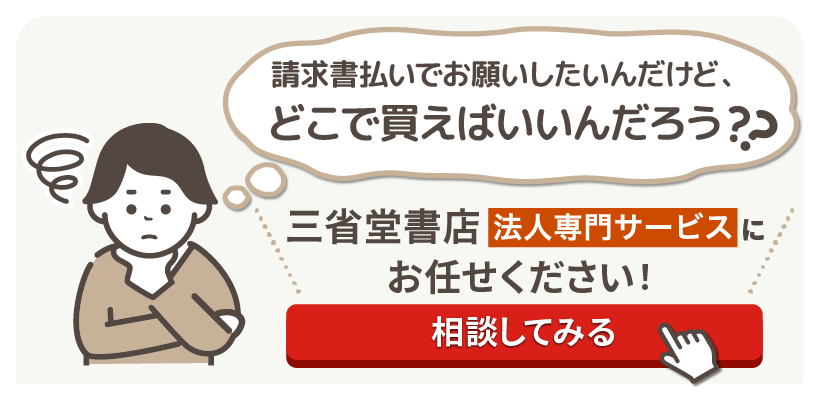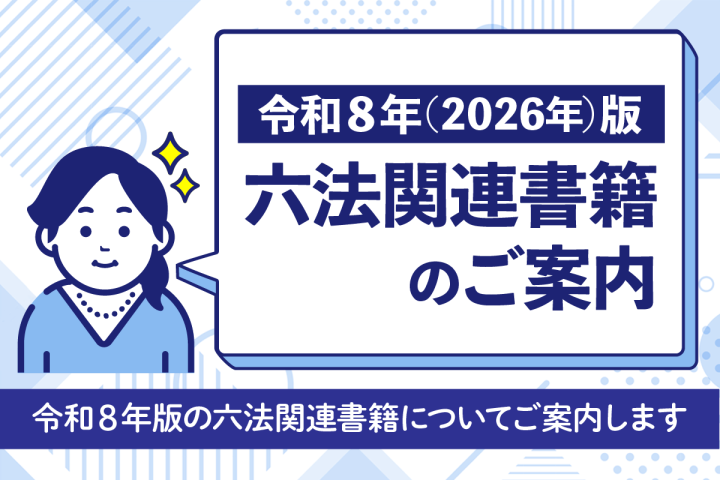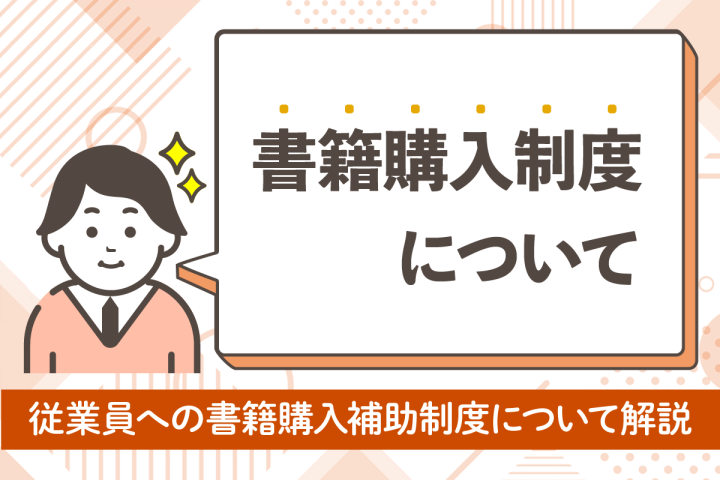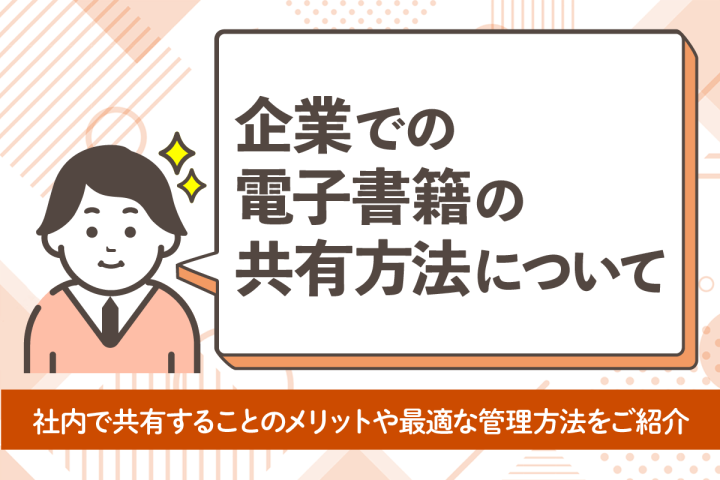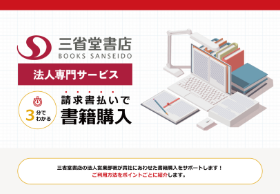書籍を請求書払いにするのは、普通?
結論から言えば、法人による書籍の請求書払いは「ごく一般的な取引手法」です。
特に
- 教育機関や公的機関、上場企業などでの定期的な購入
- 社内の稟議・発注フローにクレジットカードが使用できない場合
- 月末締め・翌月末払いなどの支払サイクルを希望する場合
のようなケースでは、多くが請求書払いとなります。
書店や出版社によって対応範囲は異なるものの、法人向けサービスやBtoB専用フォームを設けている販売元も増えており、「クレジットカードなしで書籍を購入したい」というニーズは想定済みのことが多いです。
むしろ、法人購買では請求書払いがスタンダードになりつつあるとも言えます。
書籍を請求書払いする方法とは?
請求書払いを利用する流れは、基本的に以下の通りです。
- 法人向け注文フォームや専用サイトから申込
- 請求書の宛名・送付先・希望支払条件などを記入
- 書籍が届き次第、請求書が発行される
- 指定された期日までに銀行振込などで支払い
そのほか、請求書払いを利用するには事前準備も大事になります。
請求書払いに対応している書店・サービスを確認する
まずは、書籍の購入先が請求書払いに対応しているかを確認する必要があります。
三省堂書店をはじめ、請求書払いに対応している書店・サービスではそれぞれ「法人窓口」「BtoB専用注文フォーム」などを設けています。
ECサイトでも、一部の書籍専門通販サイトで請求書払いに対応しているケースがあります。
注文時に必要な情報を事前に準備する
請求書払いで注文する際には、以下のような情報が求められるのが一般的です。
- 請求書の宛名(会社名・部署名など)
- 納品先住所
- 担当者名
- 希望納期や支払条件
- 見積書・納品書の有無
これらを事前に整理しておくと、注文手続きがスムーズに進みます。
初回取引時は「事前審査」や「前払い」の可能性も
一部の書店では、初回取引に限り「前払い(銀行振込)」が必要だったり、法人審査が行われるケースがあります。
特に高額の注文や、法人登録のない個人事業主の場合には、請求書払いの利用条件が制限されることもあるため、事前の確認が重要です。
請求書の形式と支払いフローを確認する
書店によっては、紙の請求書に加えてPDF形式での電子請求書を発行してくれるケースがあります。
経理処理の都合上、どちらのスタイルが適しているかを確認しておくとよいでしょう。
また、請求書発行日・支払期日・振込先口座情報などの詳細を確認し、自社の支払フローとずれがないかをチェックすることも忘れないようにしましょう。
参考記事:①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
書籍を請求書払いする時に、後払いできる?
書籍の請求書払いは、基本的に「後払い方式」で運用されるのが一般的です。
請求書払いとは、商品の納品後に請求書が発行され、後日(たとえば月末締め・翌月末払い)で支払う方法のこと。つまり、実質的には「後払い」の一種であり、法人のキャッシュフローにもやさしい仕組みです。
ただし、書店によっては初回注文のみ「前払い」が求められる場合や、一定金額以上の注文で後払い可となる場合もあります。
また、支払サイト(支払期限)もサービスごとに異なるため、
- 支払期日(30日以内かどうか)
- 請求書発行日と締め日の扱い
- 利用上限の設定有無
などをあらかじめ確認しておくことが大切です。
書籍を請求書払いで購入して感じたこと
上場企業の人材育成部署で、研修用の書籍を年間数百冊単位で発注しています。以前は都度クレジットカードで購入していましたが、精算の手間と承認フローのわずらわしさが大きな課題でした。
しかし請求書払いに切り替えてからは、発注〜支払いまでの処理が格段にスムーズになり、毎月の経理処理にも柔軟に対応できるようになりました。
なかでも特によかったのが、複数の部署からの注文を一括管理できることと、PDF請求書対応で印刷・回覧が不要になった点です。
導入時に少し手続きは必要でしたが、それ以上にメリットが大きく、今では社内の購買フローとして定着しています。
まとめ
法人にとって書籍購入の請求書払い、後払いは、今や珍しいことではなく、業務効率化と支払管理の観点からも非常に有用な選択肢です。
クレジットカードが使えないケースや、大量購入・継続発注を行う企業では特にメリットが大きく、対応サービスも年々充実しています。
これから導入を検討している担当者は、まずは信頼できる法人対応書店のサービスをチェックし、支払条件や納品スケジュールを確認してみましょう。
請求書払いをうまく活用することで、社内業務の効率と購買の透明性がぐっと高まるはずです。