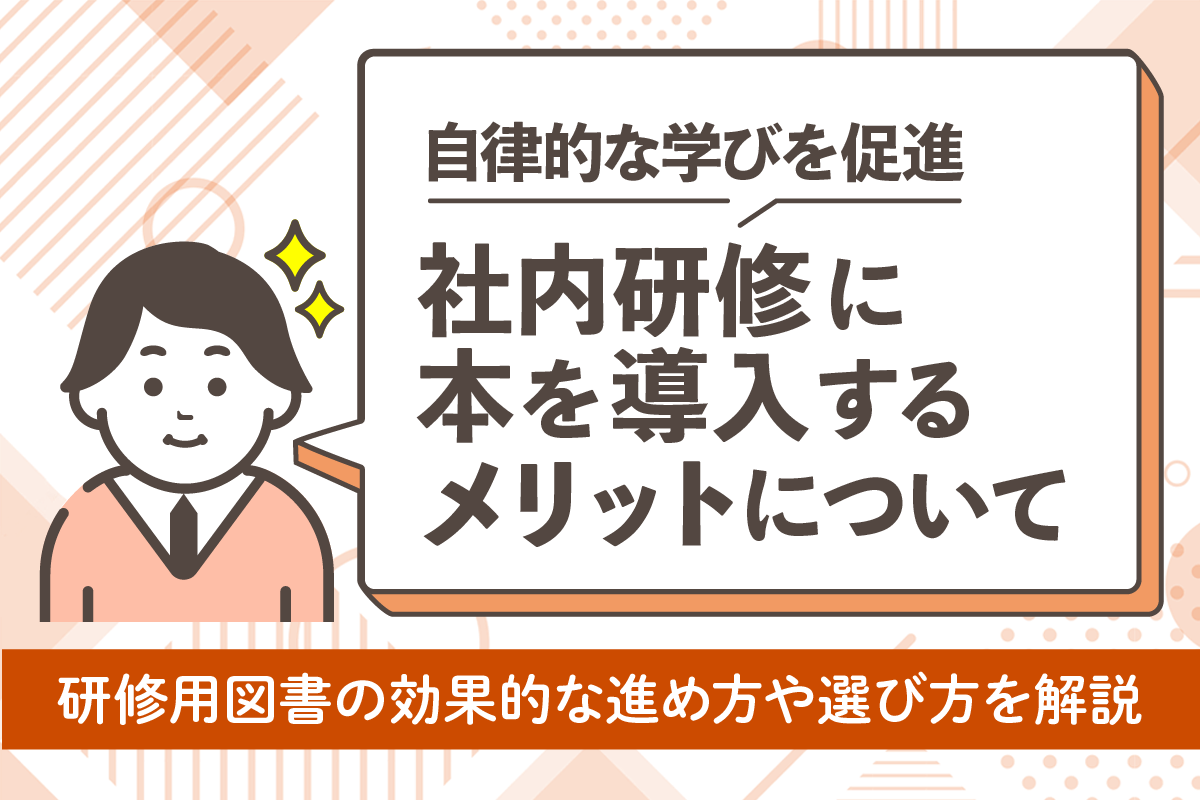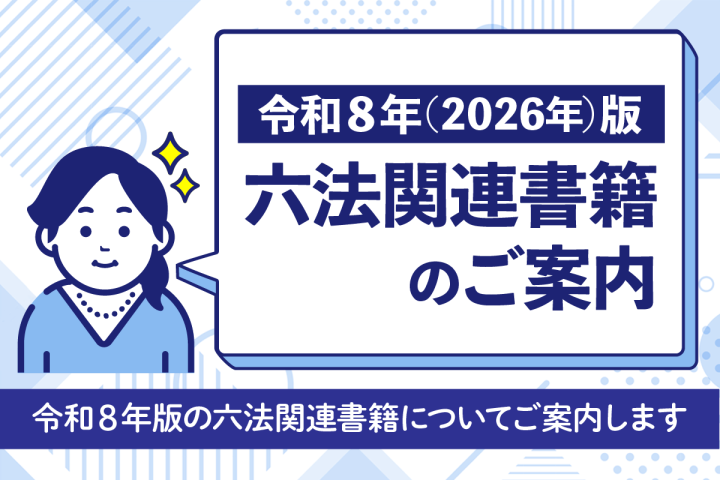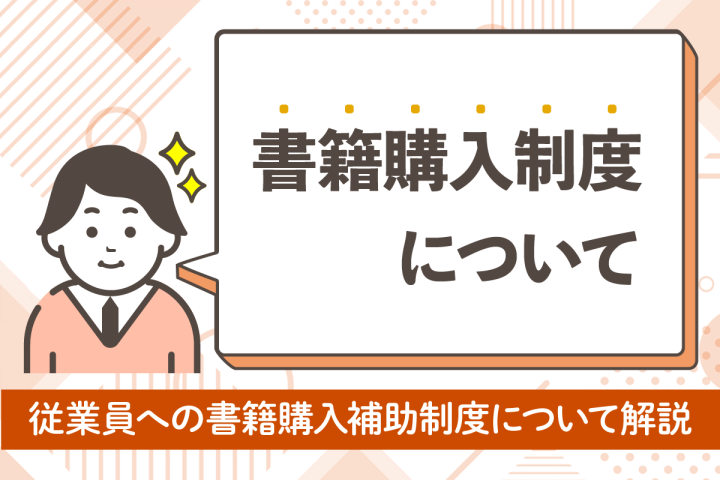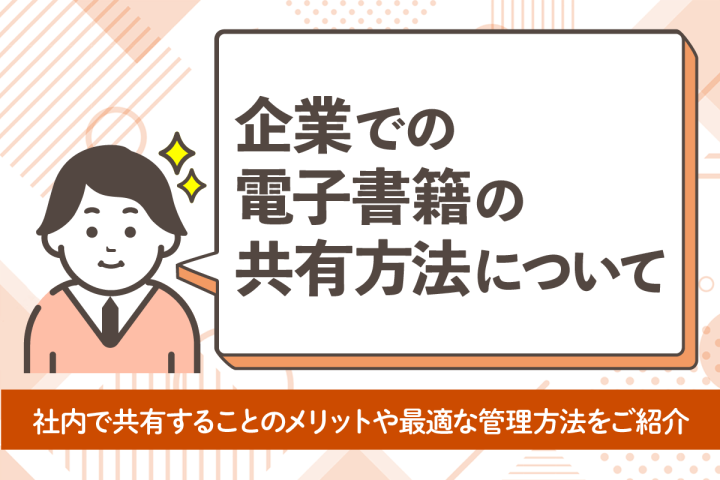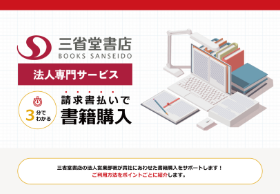企業の成長を支えるのは、社員一人ひとりの力です。そのため、多くの企業が人材育成を目的とした社内研修に力を入れています。しかし、「研修がマンネリ化している」「コストがかかる割に効果が見えにくい」といったお悩みをお持ちの研修担当者様も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、新たな一手として「本」を社内研修に導入する方法をご紹介します。具体的なメリットから進め方、おすすめの書籍まで詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
社内研修に本を導入する3つのメリット

社内研修に本を導入することは、コスト面だけでなく、社員の成長を促す上でも多くのメリットがあります。ここでは、代表的な3つのメリットについて解説します。
| メリット | 具体的な効果 |
| 体系的な知識の習得 | 専門家によって整理された知識を、自分のペースで深く学べる。 |
| 自発的な学習意欲の促進 | 読書を通じて新たな興味が湧き、自己啓発への意識が高まる。 |
| コストの抑制 | 外部研修と比較して、一人当たりの研修費用を大幅に削減できる。 |
メリット1:体系的な知識を効率的に学べる
書籍は、特定のテーマについて専門家が知識を体系的にまとめたものです。断片的な情報ではなく、背景や理論から実践方法まで一貫して学ぶことができるため、受講者はテーマに関する深い理解を得られます。また、社員がそれぞれのペースで読み進められるため、知識の定着度も高まる傾向にあります。
メリット2:社員の自発的な学習意欲を促進する
研修をきっかけに読書習慣が身につくことで、社員が自ら学びを深めていく「自己啓発」の文化を醸成できます。一冊の本から関連書籍へと興味が広がることもあり、会社から与えられる研修だけでなく、自律的にスキルアップを目指す人材の育成につながります。これは、長期的な視点で企業の成長を支える大きな力となります。
メリット3:外部研修に比べてコストを抑制できる
外部の研修サービスを利用する場合、一人あたり数万円から数十万円の費用がかかることも少なくありません。 一方、書籍であれば一冊数千円程度で、質の高い知識やノウハウを提供できます。特に、全社員を対象とするような大規模な研修の場合、このコストメリットは非常に大きくなります。
社内研修に本を導入する際の注意点
多くのメリットがある一方で、本を社内研修に導入する際にはいくつかの注意点も存在します。事前にこれらの点を理解し、対策を講じることで、研修の効果をさらに高めることができます。
| 注意点 | 必要な対策 |
| 効果の個人差 | 読書会やレポート提出など、アウトプットの機会を設けて読書を促す。 |
| インプットだけで終わってしまう | 学んだ内容を実践するワークショップや、実務での活用目標を設定する。 |
| 講師役に負担がかかる | 運営は人事部が主導し、講師役の負担を軽減するサポート体制を整える。 |
読書習慣の有無で効果に差が出やすい
当然ながら、普段から本を読む習慣がある社員とそうでない社員とでは、本から知識を吸収するスピードや深さに差が出ることがあります。読書に苦手意識を持つ社員がいることを前提に、なぜこの本を読む必要があるのか、目的を丁寧に説明することが重要です。
知識のインプットだけで終わる可能性がある
本を読むだけでは、知識が身についただけで行動変容にはつながりにくいという課題があります。研修の効果を最大化するためには、読んだ内容についてディスカッションしたり、レポートにまとめたりといったアウトプットの機会を設けることが不可欠です。これにより、知識の定着と実践への応用が促進されます。
講師役の社員に負担がかかる
研修の進行役やディスカッションのファシリテーターを特定の社員が担う場合、その社員の業務負担が増加する可能性があります。準備期間や当日の運営など、通常業務に加えて大きな負荷がかかることを考慮し、人事部が主体となってサポートする体制を整えることが大切です。
失敗しない!研修本の効果的な選び方

研修の成果は、どのような本を選ぶかに大きく左右されます。ここでは、自社の課題解決と社員の成長につながる本を選ぶための3つのポイントをご紹介します。
| 選定のポイント | 確認事項 |
| 目的の明確化 | この研修を通じて、社員にどうなってほしいのか? |
| 対象者のレベル | 新入社員向けか、管理職向けか?専門知識はどの程度必要か? |
| 内容の実践性 | 具体的な事例や、明日から使えるテクニックが紹介されているか? |
研修の目的とゴールを明確にする
まず、「なぜこの研修を行うのか」「研修後、社員にどのような状態になってほしいのか」という目的とゴールを明確にしましょう。例えば、「若手社員の論理的思考力を養う」という目的であれば、ロジカルシンキングの基本を解説した書籍が候補になります。目的が明確であれば、選ぶべき本の方向性もおのずと定まります。
対象となる社員の階層やスキルに合わせる
研修の対象者が新入社員なのか、中堅社員なのか、それとも管理職なのかによって、求められる知識やスキルは異なります。対象者の現在のレベル感や課題に合った、少し挑戦的でありながらも理解可能なレベルの本を選ぶことが、モチベーションを維持する上で重要です。
【関連記事】【2025年最新版】新卒研修に最適なマナーの学び方とおすすめ書籍 |三省堂書店法人専門サービス
実践的で分かりやすい内容か確認する
専門的すぎたり、抽象的な理論に終始したりする本は、研修教材としては不向きな場合があります。図解が多く使われている、専門用語が平易な言葉で解説されている、具体的な企業の事例が豊富に紹介されているなど、受講者が内容をイメージしやすく、実務に活かせる本を選びましょう。
本を使った社内研修の具体的な進め方
目的や書籍が決まったら、次はいよいよ研修の計画を立てます。ここでは、本の導入効果を高めるための具体的な4つのステップを紹介します。
| ステップ | 内容 | 成功のポイント |
| 1. 目的と対象者の設定 | 研修のゴールと参加者を明確にする | 経営層や現場のニーズをヒアリングし、課題を特定する |
| 2. 本の選定と配布 | 設定した目的に最適な本を選び、社員に配布する | なぜこの本を選んだのか、その背景や意図を丁寧に伝える |
| 3. アウトプットの機会 | 読書会や発表会などを企画し、学びを共有する場を設ける | 参加者が安心して発言できる、心理的安全性の高い場作りを心がける |
| 4. 振り返りとフィードバック | 研修で得た学びや今後の課題について振り返りを行う | 上司からのフィードバックや、実務での実践を促すフォローアップを実施する |
ステップ1:研修の目的と対象者を設定する
まずは、社内の課題を基に「誰に」「何を」学んでほしいのかを明確にします。例えば、「中堅社員のリーダーシップを強化する」といった具体的な目的を設定することで、研修全体の軸が定まります。
ステップ2:目的に沿った本を選定し配布する
目的が決まったら、それに最適な本を選びます。選定後は、対象者に書籍を配布します。その際、研修の目的や本から学んでほしいことを明確に伝えることで、社員は意識的に本を読むことができます。
ステップ3:アウトプットの機会を設ける
本を読んだ後、その内容を元にしたディスカッションやグループワーク、発表会などのアウトプットの機会を設けます。他者の意見を聞くことで、一人で読むだけでは得られなかった多角的な視点や新たな気づきが生まれます。
ステップ4:内容を振り返りフィードバックする
研修の最後には、アンケートやレポートで内容を振り返ります。「何を学んだか」「明日からどう活かすか」を言語化することで、学びが記憶に定着し、行動変容へとつながりやすくなります。上司や研修担当者からのフィードバックも、社員の成長を後押しします。
【関連記事】【2025年最新版】新入社員研修とは?目的・内容からプログラム設計、成功のコツまで徹底解説 |三省堂書店法人専門サービス
【階層別】社内研修におすすめの本
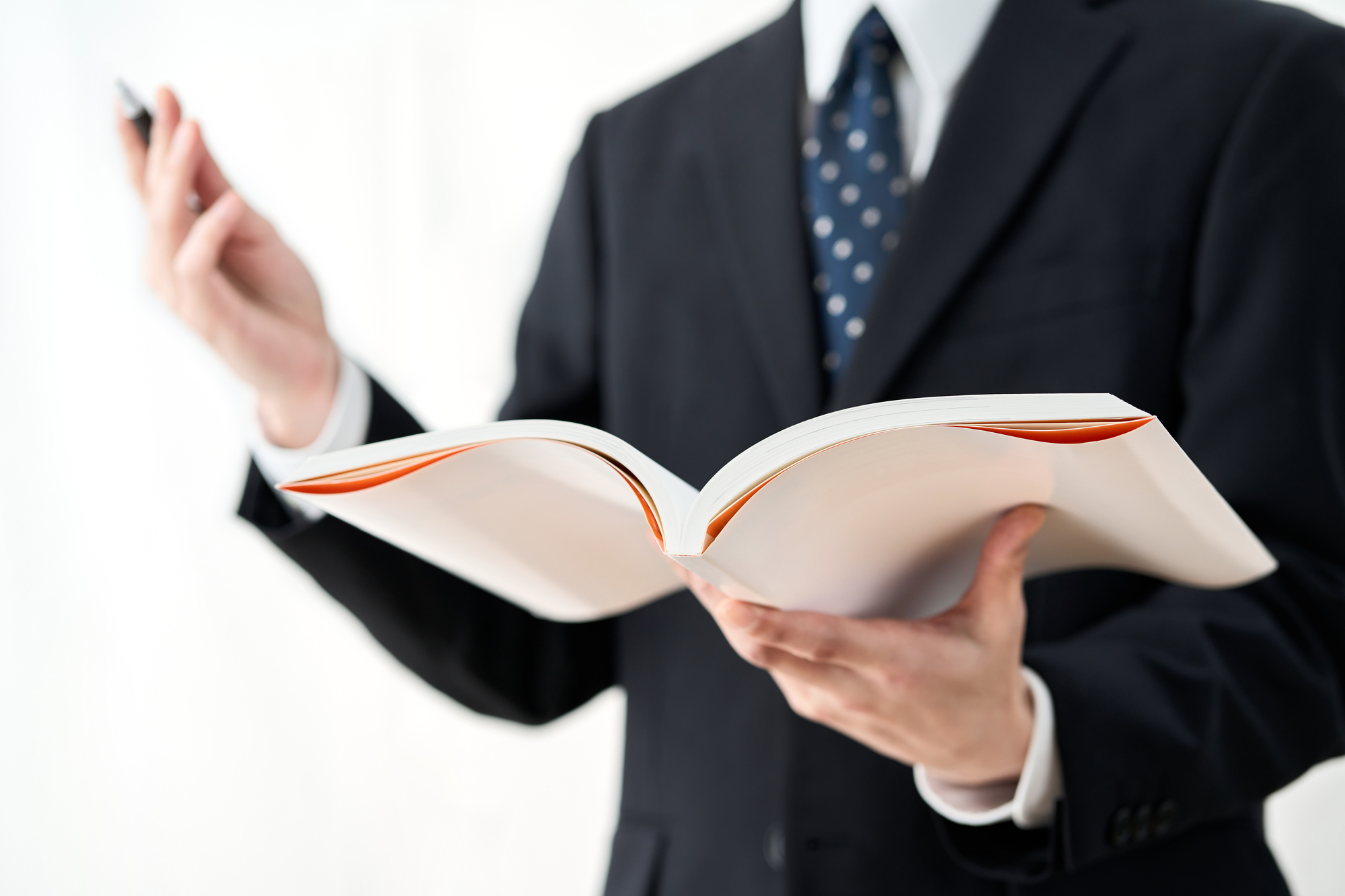
ここでは、階層別にどのようなテーマの本が適しているか、具体例を交えてご紹介します。自社の状況に合わせて、最適な一冊を見つける参考にしてください。
| 階層 | 求められるスキルと書籍テーマの例 |
| 新入社員 | ビジネスマナー
ロジカルシンキング 仕事の進め方の基本 |
| 中堅社員 | リーダーシップ
コーチング 問題解決能力 後輩指導 |
| 管理職 | チームマネジメント
組織開発 戦略策定 人材育成 |
【関連記事】|三省堂書店法人専門サービス
新入社員向けおすすめ本
新入社員には、社会人としての基礎を固めるための本がおすすめです。『入社1年目の教科書』のように、仕事への向き合い方や基本的なビジネスマナーを網羅的に学べる一冊は、多くの企業で導入されています。
中堅社員向けおすすめ本
チームの中核を担う中堅社員には、後輩指導やリーダーシップに関する本が有効です。例えば、『この1冊ですべてわかる 新版 コーチングの基本』などのコーチングの基本的な考え方やスキルを解説した本は、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献します。
参考:この1冊ですべてわかる 新版 コーチングの基本|日本実業出版社
管理職向けおすすめ本
管理職には、組織全体を動かすためのマネジメントや戦略思考に関する本が求められます。メンバーの能力を最大限に引き出すためのチームビルディングや、変化の激しい時代に対応するための組織論など、より高い視座からの学びが必要です。例えば、「マネジメントの父」と呼ばれるドラッカーによる『マネジメント【エッセンシャル版】基本と原則』などが人気です。
参考:マネジメント【エッセンシャル版】ー基本と原則|ダイヤモンド社
関連記事:【2025年最新版】新卒研修に最適なマナーの学び方とおすすめ書籍 |三省堂書店法人専門サービス
本を使った社内研修の企業事例
実際に本を研修に導入し、成功している企業は数多く存在します。ここでは、その一例として株式会社サイバーエージェントの取り組みを紹介します。
株式会社サイバーエージェントの事例
同社の常務執行役員CHOである曽山哲人氏の著書『若手育成の教科書 サイバーエージェント式 人が育つ「抜擢メソッド」』は、社内の人材育成ノウハウを体系化したものです。この書籍の内容は、実際の社内研修やマネジメントにも活かされており、「育てる」のではなく「育つ環境を整える」という考え方が社内に浸透しています。自社の人材育成哲学を本という形で明文化し、社内外に示すことで、育成文化の醸成と企業のブランディングを両立させている好事例です。
参考:若手育成の教科書ーサイバーエージェント式 人が育つ「抜擢メソッド」|ダイヤモンド社
まとめ
本記事では、社内研修に本を導入するメリットや具体的な進め方、注意点について解説しました。本を活用した研修は、コストを抑えつつ、社員の体系的な知識習得と自律的な学習意欲の向上を同時に実現できる、非常に費用対効果の高い手法です。
本をただ配布して終わりにするのではなく、アウトプットの機会や振り返りの場を設けることで、その効果を最大限に高めることができます。この記事を参考に、ぜひ貴社の人材育成に本の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
三省堂書店の法人専門サービスなら、研修テーマに最適な本の選書アドバイスから大量購入まで、専門スタッフが全面サポートいたします。請求書払いや複数拠点への配送にも対応し、メール1本で研修用書籍の導入が完了。140年の実績が裏付ける安心のサービスをぜひご活用ください。
資料ダウンロード | 【見積書発行・請求書払いOK】法人の書籍購入は三省堂書店